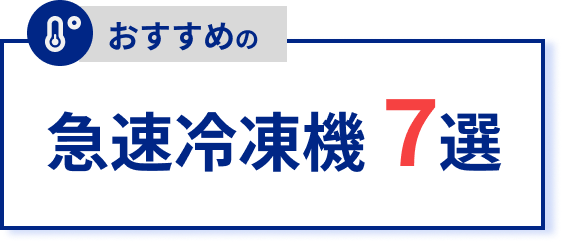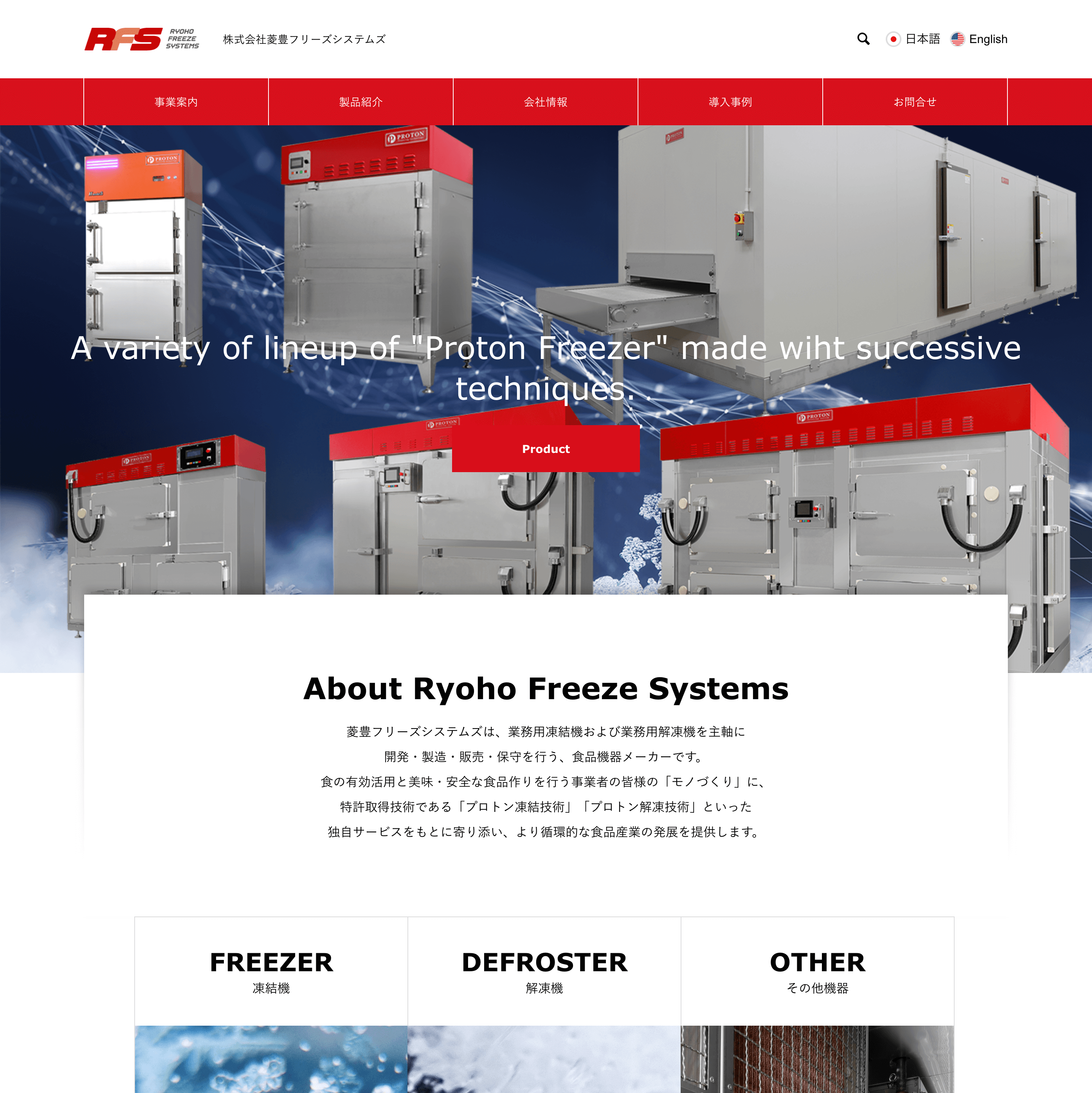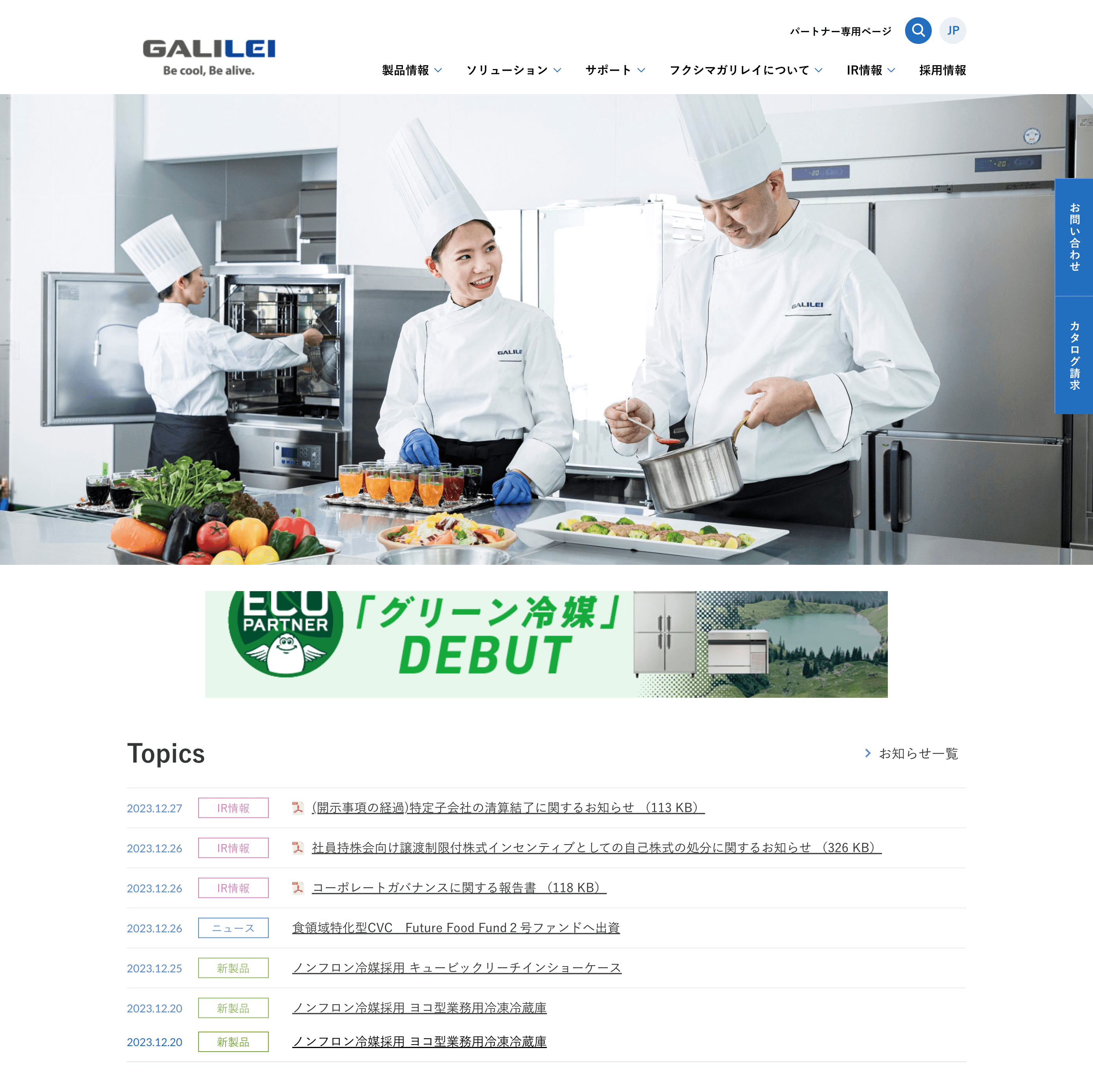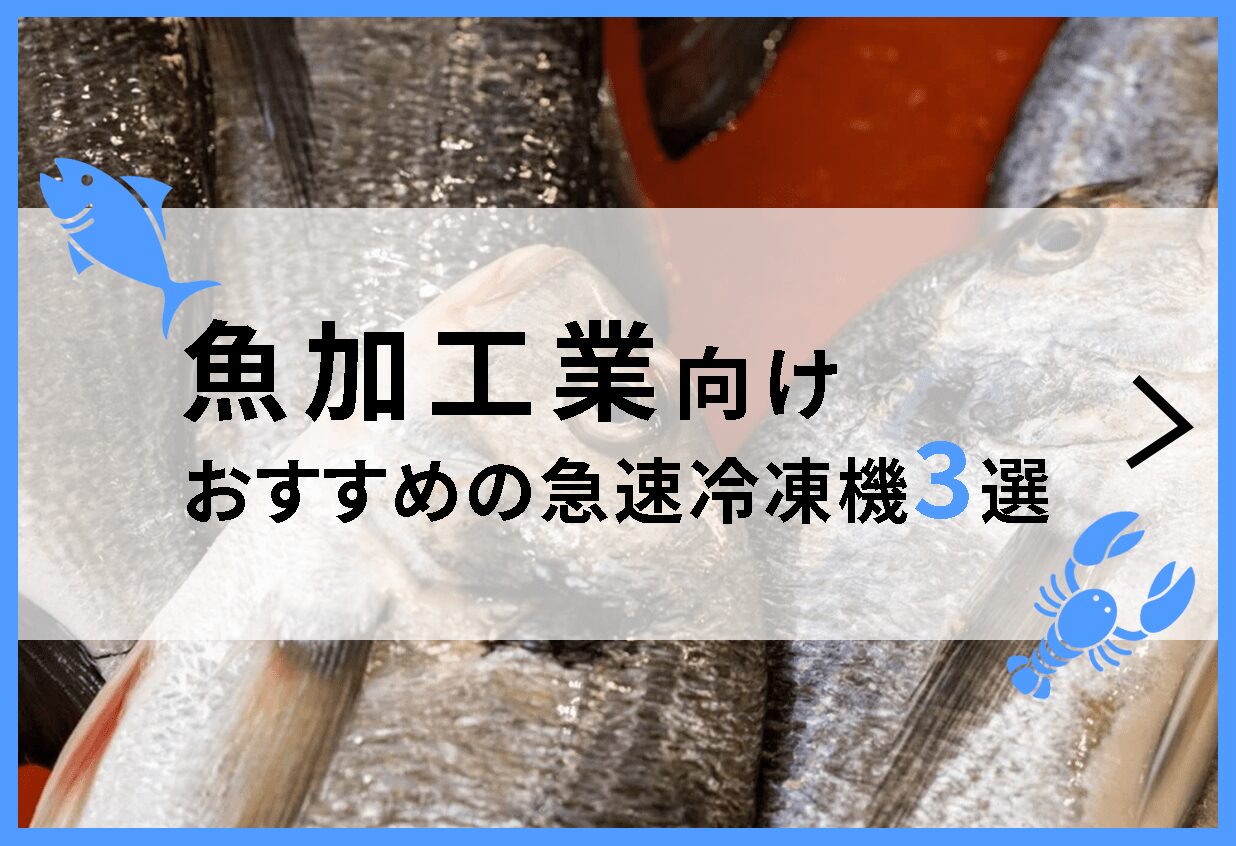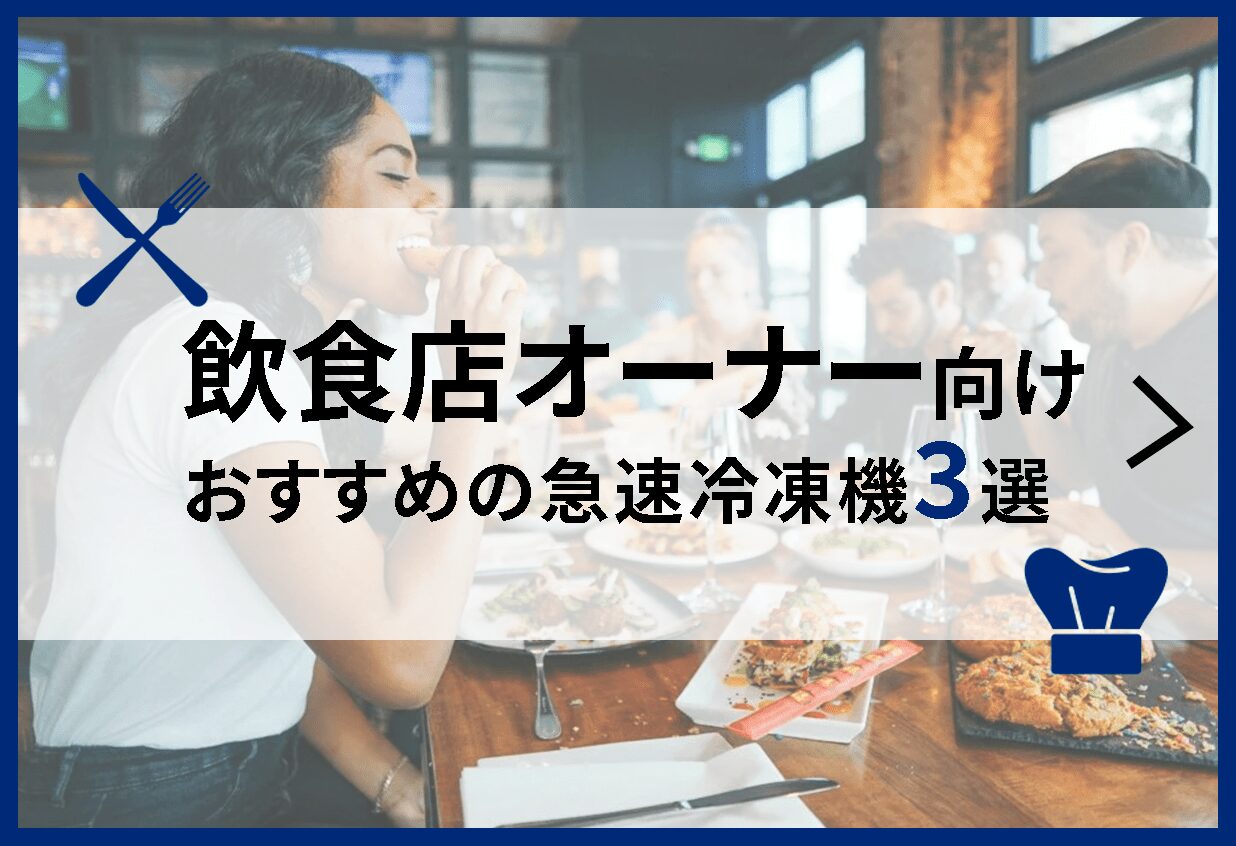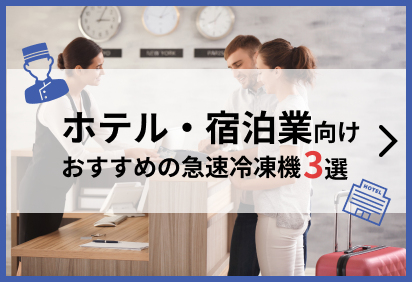食材や調理後の食品を冷凍したい方にとって、ショックフリーザーはなくてはならない存在です。特に、食材を扱う業種では、衛生管理や食中毒対策として、ショックフリーザーは重宝するのではないでしょうか。今回は、おすすめのショックフリーザーを3つ紹介します。それぞれ特徴が異なるので、ぜひ使い方に合ったものを探してみてください。
株式会社コガサン「3Dフリーザー」

株式会社コガサン「3Dフリーザー」の基本情報
| 会社名 | 株式会社コガサン |
| 住所 | 山口県下関市彦島迫町1丁目4番10号 |
| 電話番号 | 083-267-2811 |
株式会社コガサンは、昭和44年に設立された株式会社です。主に食品機器の製造を行っています。株式会社コガサンが扱っているのは「3Dフリーザー」で、ブラストチラーとショックフリーザーを使い分けできることが特徴です。
また、冷凍冷却テストを体験できるので、気になる方はぜひ体験してみてください。さらに、ランニングコストを30%削減可能な点もメリットです。店舗運営に関わるコストを削減したい場合は、ぜひ株式会社コガサンの3Dフリーザーを検討してみましょう。
ブラストチラーとショックフリーザーを使い分け
株式会社コガサンの3Dフリーザーは、同じ急速冷凍でも「ブラストチラー」と「ショックフリーザー」を使い分けて使用できます。粗熱を取りたい時はブラストチラーを活用し、冷たい料理や粗熱が取れた料理は、ショックフリーザーを使用することが可能です。
料理の状態によって最適なモードを選べる点は、株式会社コガサンの3Dフリーザーの大きなメリットだと言えるでしょう。さらに、株式会社コガサンの3Dフリーザーはフリーズモードとチラーモードを使い分けることが可能です。
フリーズモードは、芯温-18℃以下まで一気に冷凍します。おいしさを保ったまま、急速に冷凍したい食品は、フリーズモードを使用することで鮮度を保ちながら長期保存や発送が可能です。
チラーモードは、芯温3℃以下まで一気に冷凍するモードです。保存や発送をしない料理はチラーモードを活用することで、食品の安全性と調理の効率化を両立可能です。モードを使い分けることで、快適な調理環境を実現できます。
冷凍・冷却テストを体験可能
株式会社コガサンの3Dフリーザーは、購入前にテストや体験が可能です。体験の方法は、訪問テスト、郵送テスト、ご来訪テストが可能です。それぞれ、詳しく解説します。
訪問テストは、テスト機器を店舗まで持ってきてもらいテストをする方法です。冷凍・冷却テストを、自前の食材を利用して実験できます。
郵送テストは、テストしてほしい食材を株式会社コガサンに郵送し、3D冷凍してもらえる方法です。サンプルを郵送するだけでテストしてもらえるので、手軽にテストを試したい方は利用を検討してみましょう。
ご来訪テストは、ショールームや各営業所に足を運んでテストをする方法です。お近くにショールームや営業所がある場合におすすめです。ただし、ショールームや営業所によって扱っている機器が異なるので、事前に確認しましょう。
ランニングコストを約30%削減
株式会社コガサンの3Dフリーザーは、凍結後の水分の目減りが少ないのが特徴です。凍結後に目減りしないので、事前に原料を増やしておくなどの対策が必要ありません。凍結用に特別な料理を作る必要がないので、調理の手間も省けるでしょう。
また、原料を増やす必要がないので、ランニングコストを削減できます。特に、現在凍結用に調理を行っている会社では、大きなコスト削減になるでしょう。
ホシザキ「HBC series」

ホシザキ「HBC series」の基本情報
| 会社名 | ホシザキ株式会社 |
| 住所 | 愛知県豊明市栄町南館3-16 |
| 電話番号 | 0562-97-2111 |
ホシザキは、昭和22年に設立された会社です。製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機の製造と販売を行っている会社です。
ホシザキ「HBC series」は、自動乾燥機能や自動洗浄機能があります。日々のお手入れを楽にしたい方は、ホシザキ「HBC series」の購入を検討してみましょう。AR設置シミュレーションも可能なので、手軽に導入を検討できます。
AR設置シミュレーションが可能
AR設置シミュレーションでは、実際に製品を厨房に置いた状態をシミュレーションできます。製品を購入する前に、アプリインストールなどをせずに体験できるので、ぜひ一度試してみてください。
AR設置シミュレーションは、スマートフォンやタブレットで使用可能です。ただし、AR設置シミュレーションを体験できる製品は限られている点に注意しましょう。
冷凍モードが選べる
ホシザキ「HBC series」は、ソフトチル・ハードチル・ショックフリーズからモードを選べます。食材によって冷凍モードを選べるので、食材ごとに管理したい場合におすすめです。
また、芯温制御、庫内温度制御の機能も搭載されているので、快適に温度管理ができる点も魅力です。食品に合わせて使い分けられる風速の機能も搭載されているので、使い勝手を優先したい方は、ホシザキ「HBC series」を検討してみましょう。
自動洗浄機能を搭載可能
ホシザキ「HBC series」は、オプションで自動洗浄機能をつけることができます。自動洗浄機能は、使い終わった後にワンタッチで庫内の洗浄が完了するオプションです。冷却器用の洗浄ノズルも搭載されているので、庫内を清潔に保ちたい方におすすめです。
自動洗浄機能が搭載されていない製品であっても、庫内は丸洗い可能です。また、自動乾燥機能が標準搭載されているので、食品の衛生管理を徹底したい方にも安心です。
「超低温ショックフリーザー」espec

「超低温ショックフリーザー」especの基本情報
| 会社名 | espec |
especの超低温ショックフリーザーは、超低音で鮮度を保ちながら急速冷凍ができることが特徴です。また、冷凍から再加熱まで行うことができるので、機能が多いショックフリーザーが必要な場合は、快適に使用できるでしょう。
また、especはテストキッチンを使用して、メニュー開発や実機見学が可能です。実際に目で見て、使用してショックフリーザーを選びたい場合には、especのテストキッチンに足を運んでみてください。
メニュー開発や実機見学が可能
especの超低温ショックフリーザーは、エスペック神戸R&Dセンターにあるテストキッチンに設置してあります。テストキッチンでは、メニュー開発や実機見学を行うことが可能です。especの超低温ショックフリーザーを実際に使ってみたいという方は、ぜひテストキッチンの利用を検討してみてください。
また、especのアフターサービス拠点は、全国15箇所に存在しています。さらに、オンラインサポートや保守契約サービスのプランも用意されているので、ショックフリーザーのアフターサービスが気になる方も安心です。
超低温で鮮度を保ちながら急速冷凍
especの超低温ショックフリーザーは、-70℃の超低温で食材を凍結します。超低音で食材を凍結することにより、氷結晶サイズが成長抑制されて解凍後のドリップを抑えることが可能です。
さらに、especの超低温ショックフリーザーには、送風機構が搭載されています。送風機構によ、庫内の低風速化を実現することで食品の乾燥を抑えることが可能です。especの超低温ショックフリーザーであれば、20分で食材の凍結が完了し、ドリップがほぼ出ない、品質を保った凍結が可能になります。
冷凍から再加熱まで一台で対応
especの超低温ショックフリーザーは、-70℃ ~ +100℃という幅広い温度帯をプログラムすることが可能です。急速冷凍した食材を保管し、解凍、再加熱までできる点は、especの超低温ショックフリーザーの大きなメリットだと言えるでしょう。
特に、厨房に様々な機器を起きたくない場合や、厨房自体が狭い場合は、especの超低温ショックフリーザーがおすすめです。必要な機能を1台で賄えるので、機会を増やしたくない場合は、especの超低温ショックフリーザーの導入を検討してみましょう。
ショックフリーザーとは?
まずは、ショックフリーザーとはそもそも何かについてご紹介します。意外と知らない、または勘違いしている方も少なくないので、この機会に正しく理解しておきましょう。
食材をすばやく冷やすための機械「ショックフリーザー」
ショックフリーザーとは、業務用の急速冷凍機のことを指します。一般的な冷凍庫と違って、食材を短時間で一気に冷やすための専用機械です。
食品を早く冷やすことで、菌の繁殖を防ぎ、味や見た目、栄養価を保つことができます。冷凍食品の品質を保つためにとても重要な機器です。
なお、呼び方はいろいろあり「急速冷凍機」「急速凍結庫」「瞬間冷凍機」「ブラストチラー」などと呼ばれることもありますが、どれも基本的には同じ仕組みの機械を指しています。
ショックフリーザーは、主に-30℃から-40℃ほどの冷たい風を直接食品に当てて冷やす方法で使われています。この冷たい風で一気に冷やす方法を「エアブラスト式」と呼び、現在販売されているショックフリーザーの多くがこの方式を採用しています。
ショックフリーザーは冷凍だけではない
ショックフリーザーと聞くと「冷凍専用の機械」と思われがちですが、実は冷却を目的とした機器もあります。
たとえば、調理後のアツアツの食品を常温で放置すると、菌が増えやすくなってしまいます。これを防ぐために、食品を10℃~20℃くらいまで一気に冷やすことで、菌の繁殖を抑えるという使い方もあるのです。
このように「冷凍」ではなく「冷却」を目的としたショックフリーザーも多く存在します。そのため、導入を考える際には、目的に合った機種を選ぶことがとても重要です。
単に温度が低ければ良いというわけではなく「何度まで下がるのか」「どのくらいの時間で冷えるのか」「冷凍まで対応しているか」など、仕様をしっかり確認することが失敗を防ぐポイントです。
小型のショックフリーザーも登場
近年では、技術の進歩により小型のショックフリーザーも販売されるようになっています。
これまで業務用の大きなサイズしかなかったものが、100Vの家庭用電源で動くタイプも出てきました。小さな飲食店や、テイクアウトに力を入れる店舗などにとっては、導入しやすくなってきています。
ただし、小型であるぶん一度に冷やせる量は限られており、大量の食材を扱う場合には不向きです。また、急速冷却は可能でも「冷凍までは対応していない」というケースもあるため、目的に合った機器選びが重要です。
価格についても、小型のものであれば100万円ほどから購入可能ですが、一般的な業務用サイズになると400万円以上になることもあります。
コストに見合った使い方をするためにも、事前にどのような用途で使うのかを明確にしておくとよいでしょう。
導入には知識が必要!正しい使い方で品質を守る
ショックフリーザーは、冷凍や冷却の質を高めることができる便利な機器ですが、正しく使わなければかえって品質が落ちることもあります。
たとえば、ただ食材を入れて冷やすだけでは、中までしっかり冷えず、表面だけ凍ってしまったり、水分が飛んでしまったりすることもあります。これでは食材の品質や風味が損なわれてしまうでしょう。
また、使い方を間違えることで作業効率が悪くなったり、調理の工程に無駄が生じたりすることもあります。
こうした失敗を避けるためには、導入前に専門家からアドバイスを受けたり、取扱説明書をよく読んだりすることが大切です。
さらに、使用する人全員が正しい知識を持っておくことも重要です。近年では、冷凍食品の需要が増えており、ショックフリーザーの導入を検討する飲食店や食品工場が増えています。
とくに、作りたての味をそのまま届けたいと考える店舗にとって、ショックフリーザーは強い味方になります。たとえば、お弁当や惣菜を冷凍販売する場合でも、しっかりと品質を保ったまま提供できるため、お客様の満足度も高まります。
ブラストチラーとの違いは?
ここでは、ショックフリーザーとよく似た言葉として使われる「ブラストチラー」との違いについてご紹介します。どちらも食品をすばやく冷やすための業務用機器ですが、実は目的や使い方に少し違いがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
ショックフリーザーとブラストチラーは同じ?違う?
まず最初にお伝えしておきたいのは「ショックフリーザー」も「ブラストチラー」も、どちらも業務用の急速冷却・冷凍のための機械を指すということです。
どちらかが間違いというわけではなく、呼び方の違いであることが多く、メーカーでもこの2つをはっきり分けていないケースが多いのです。
たとえば「ショックフリーザー/ブラストチラー」という名前で、1台で冷却も冷凍もできる機種が販売されていることもあります。
ただし、名前にある「フリーザー」は英語で「凍らせる機械」、「チラー」は「冷やす機械」という意味があり、それに沿って使い分けている人も少なくありません。
具体的には、食品をマイナス温度まで下げて凍らせる場合はショックフリーザー、食品を0℃以上に冷やして菌の繁殖を抑える目的で使う場合はブラストチラーと呼び分けることがあります。
このように、言葉としては似ていますが、「目的」が少し異なることを理解しておくとよいでしょう。
機能の違いは?冷却か冷凍かがポイント
ショックフリーザーとブラストチラーの大きな違いは「最終的に何度まで下げるのか」という点です。
ブラストチラーは、加熱調理した食品を冷蔵温度帯、つまり0℃〜+3℃程度まで短時間で冷やすことを目的としています。
食品がアツアツの状態で放置されると、菌が繁殖しやすくなり、とくに温度が30〜40℃のあいだは菌が増えやすいため、この温度帯をできるだけ早く通過させる必要があります。
そこでブラストチラーは強力な冷風を使って、この菌が増える温度帯を一気に通過させるのが得意です。
一方、ショックフリーザーは、食品を0℃以下、つまり凍る温度まで冷やすことを目的としています。-30℃〜-40℃の冷風を食品に当てて、できるだけ短時間で凍結させる仕組みです。
食品の中に含まれる水分は、ゆっくり凍らせると氷の結晶が大きくなり、細胞を壊してしまいます。その結果、解凍したときに水分が抜けて、味も食感も悪くなってしまうのです。
そこでショックフリーザーは急速に凍らせることで、氷の粒を細かくし、食品の品質を保ちやすくします。冷凍の質を高めるためには、この「凍るスピード」がとても重要なのです。
冷凍庫との違いは?「冷やす目的」が違う
よくある疑問として「それなら普通の冷凍庫でもいいのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、ショックフリーザーやブラストチラーと冷凍庫は、使い方の目的がまったく異なります。
家庭用や業務用の一般的な冷凍庫は「保存する」ことが目的です。冷凍庫はすでに冷凍された食品を保管するために設計されており、内部の温度は低くても、風の流れがなく、食品を素早く冷やす構造にはなっていません。
一方で、ショックフリーザーやブラストチラーは、短時間で一気に冷やす、または凍らせることを目的とした機械です。内部では強い風を食品に直接当てることで、スピーディに温度を下げられます。
これによって、菌の増殖を抑えたり、冷凍後の品質を保ったりすることが可能になります。
ショックフリーザーとブラストチラーをどう使い分けるか
ショックフリーザーとブラストチラーは、1台で両方の機能を備えているものも多くあります。しかし、実際に導入する際には「何をしたいのか」をはっきりさせることが大切です。
たとえば、調理後の食品をチルド状態まで冷やしてそのまま提供したい、または翌日まで冷蔵保存したいという場合は、ブラストチラー機能だけで十分なことがあります。
一方、食品を凍らせて長期保存したい、冷凍弁当や冷凍惣菜の製造に使いたい、解凍後も味や見た目を損ないたくないという場合は、ショックフリーザー機能が必要です。
また、ショックフリーザーの中には冷却機能は強いけれど、冷凍機能は弱いといった機種も存在します。
そのため、販売店やメーカーに「この機械は冷凍できますか?」「何度まで下がりますか?」「何分でどのくらい冷えますか?」といった具体的な質問をすることが重要です。
言葉だけにとらわれず、実際の性能をしっかりチェックしておくことで、用途に合った機種を選ぶことができます。
まとめ
業務用ショックフリーザーは、製品やメーカーによって特徴が異なります。また、厨房や調理する料理、凍結したい食材によっても、必要なショックフリーザーが変わってくるでしょう。今回紹介したそれぞれのメーカーで、実機見学が可能なので、気になる方はぜひ問い合わせをしてみましょう。
- ジャンルを問わない急速冷凍機
-
3Dフリーザー/株式会社コガサン
 引用元:https://kogasun.com/
引用元:https://kogasun.com/3Dフリーザーは、世界初の特許技術による冷凍で食品の美味しさをキープしたまま保存できる点が食品業界で評価を得ています。
繊細な飾りつけや、従来では冷凍ができないと思われていた食品など、「冷凍ができれば叶うのに…」と販路拡大や大量生産を諦めていた食品事業者の方におすすめしたい急速冷凍機です。